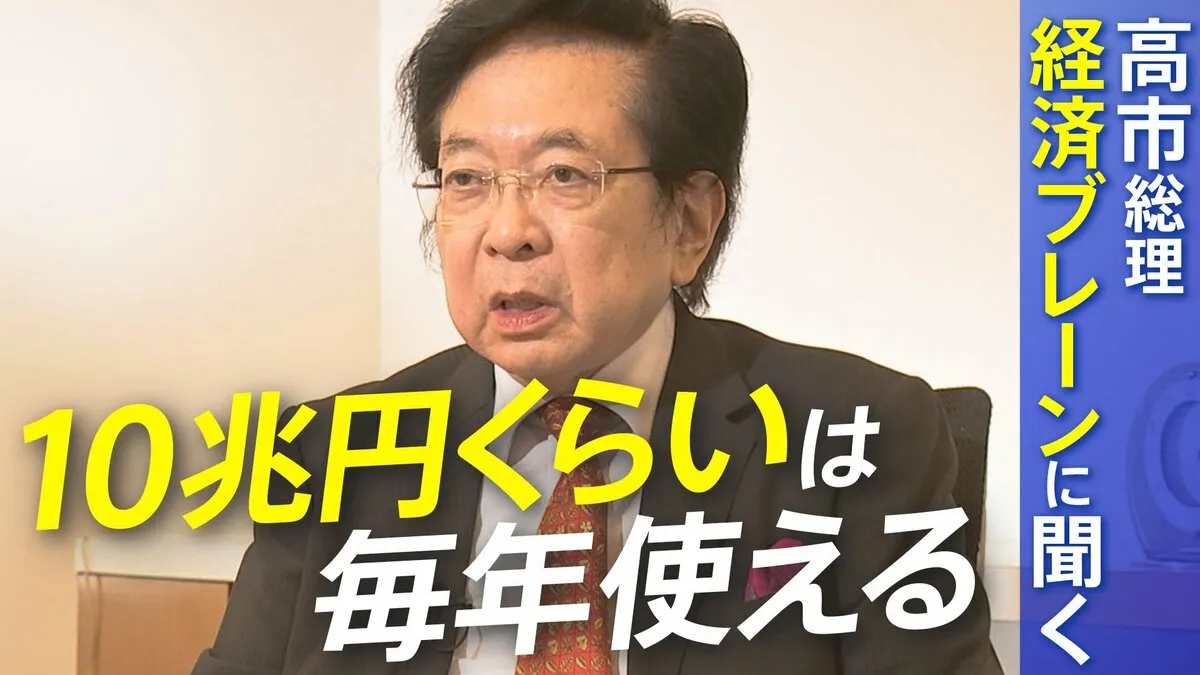
高市政権の経済政策はどうなるのか?安倍政権のもとで内閣官房参与を務め、現在は高市早苗氏に政策提言をしている本田悦朗氏に聞きました(取材は10月24日に実施しました)。
【写真を見る】高市早苗総理の経済ブレーン・本田悦朗氏に聞く経済政策と日本経済の未来
「年10兆円の余裕がある」高市総理のブレーン語る日本経済のいま
ーー高市さんに最初にお会いになったり密に意見交換をしたりするようになったのはいつごろですか?
昨年の総裁選挙の前ですね。具体的にいつ頃かというのはよく覚えていないんですが、昨年の最初ぐらいから高市さんは照準を総裁選挙に絞っていらっしゃいましたから。特に私は消費税の減税に関心を持っていますのでそこはよく議論いたしました。
ーー一番最近お会いになったのはいつですか?
1か月ぐらい前でしょうか。私だけではなくて、エコノミスト数人、それから支援者の方も含めて、複数名でレストランの食卓を囲んで。そのときの中心の課題は、やはり財政の持続可能性、それから財政余力。あとどれだけ財政を新規政策あるいは減税に使っても、日本の財政は健全さを維持できるかと言ったところにやはり高市さんは関心をお持ちになっていて。
というのは、やっぱり新しい政策をやりたいんですね。やる場合には財政資金が要りますので、どこまで余裕があるのかということを具体的な数字で示して欲しいと。それをご説明申し上げたということでありますね。
ーー具体的にどのようなアドバイスをされたんでしょうか?
まず財政の健全性とは何かというところから出発しないといけません。今の財政状況、財政運営が健全であれば、このままそれを続けられますが、問題は何が健全な財政なのかという定義です。これが財務省と、我々積極財政を主張する者との間でずれがあるんです。
財務省のお考えはプライマリーバランスの黒字化。いまは来年度中に黒字化を実現するということをおっしゃっています。
国債を発行するとそれが毎年蓄積していきます。これは債務残高と言いますが、それと同時に日本の政府は世界で最大級の金融資産を持っています。
いま日本はG7の主要先進国の中でほぼ唯一、純債務残高の対名目GDP比が下降しています。この下降している状態を維持することは至上命題です。これが発散してしまうといつかの時点で日本の財政は破綻するかもしれない。
しかし、今の運営を続けていけばゆっくり下がっていく。そういう状態を続けることを前提にして、あとどれぐらい財政出動ができるかということを計算したんですね。
その結果、最大限見積もって15兆を出せます。
ただしギリギリまでいってしまうと、リーマン・ショックなどのそういうショックがあったときに大変なことになるので安全を見込んでも10兆円くらいは毎年使えますと。新規の政策、あるいは減税に使えます。新しいことをするのに10兆円の余裕がありますということなんです。
例えば、個人的な考えですが食料品の消費税はゼロにするべきだと考えています。そのために必要な財源は約5兆円いるんですね。そうすると10兆円の中に収まってますのでやろうと思ったらできるんです。
ただし、子育て支援とか教育支援とか人材育成とか、新しい事業、スタートアップの支援とか色々なところに資金ニーズがあって消費税減税だけに使うわけにいかないので、1年じゃなくて、2年計画でもってその財源を調達していくというのが現実的です。
いずれにしても、財源がないという心配は要らないです。それだけの余裕がある。
経済対策の一方で…財政拡張がはらむリスクは?
ーー高市総理は物価高対策を最優先にするとのことですが、今回の経済対策はどれくらいの規模を想定していますか?
これから議論を進めていきますので全体の規模感というのはまだ想定されてないような気がしますが、最初にまず始めないといけないのはガソリン税の暫定税率の廃止。これは1兆円かかります。それから、軽油引取税で大体0.5あるいは0.6兆円、合わせて1.6兆円。これはまず最初にやりましょうと。それ以外にも物価対策としてどういうものを組み込んでいくかによってずいぶん予算規模が変わってきます。
もうデフレはほぼ完全に脱却しているので、あとはこの成長力をどこまで維持するかという意味では、少し大きめの補正予算を組んで欲しいなと。ただ、なかなか具体的にいくらだろうというのは難しいですね。
ーー財政拡張することで、トラスショックのようなことが起きる懸念はないんでしょうか?
トラスショックのことはよく伺います。
トラスショックが起こったときのマクロ経済環境は一体どうだったかと。そのときは、需要超過でした。潜在的供給能力以上の需要があって、だからこそ7、8%のインフレ率が起こってきた。
そのときにトラスさんは何をしようとしたかというと、減税計画を発表したんです。これはさかさまじゃないですか。そんなに需要が多いなら、ちょっと水をかける程度がちょうどいいんです。もっと減税するということはもっと需要を増やすということですから、それは通貨も国債も混乱します。だからトラスさんが失敗したのは、政策そのものがいいかどうかという問題ではなくて、マクロ環境とその政策がフィットしなかったからだと思います。
大体、財務省が我々に対して議論をしてくるときは、トラスショックかギリシャショックなんですよ。でも日本とは関係ありません。ギリシャショックは自国通貨がなかったからなんです。外国からお金を借りるしかなかった。日本は自国通貨ですから全然心配いらないですね。
問われる政府と日銀の連携 高市総理発言の真意は?
ーー10月の金融政策決定会合を控えていますが、日銀の利上げの判断を本田さんはどうご覧になっていますか?
最終的には政策決定会合で審議委員と総裁副総裁がお決めになることですが、日銀法は3条と4条の構造があって、3条は日銀は独立してこの業務を行うと書いてあり、4条は日銀と政府は連携して仕事をしなさいと書いてあります。
私がみる限り高市さんはやっぱり4条を重視するんです。日銀がもちろん独立して金利を決めますが、運営にあたっては政府と密に連携をとってくださいと。
例えば安倍総理は、黒田前総裁と定期的に非公式ランチをとっておられたんです。それぞれ経済認識を意見交換して、認識を共有できるようにいつも努力されていました。ところが岸田さん、石破さんがやった形跡があまりないような気がするんです。だからぜひ高市さんには復活してほしいです。
場合によっては政府サイドは財務大臣がいいのかもしれません。片山さつきさんは優秀な方なので、総理がやられるのがいいのか、財務大臣がやられるのがいいのかは別として、やっぱり政府と中央銀行は、連絡を密にするということが必要だと思います。
その点から考えると、日銀の次の政策決定会合はもうすぐです。(※10月の金融政策決定会合は29日・30日に実施)外交日程も詰まっていますので今回はコミュニケーションをとる時間がないのかなと。そうすると次の利上げっていうのはいつかというと、可能性があるのは12月ということになりますよね。12月に上げた方がいいという意味ではなく、あるとしたら12月が最初の可能性かなということです。
ーー高市さんの「政府も金融政策の責任を持つ」との発言はどう解釈したらいいでしょうか?
真意は私もよくわかりませんが、筋論を言えば、日銀は一体何をするところなのか、その目的は政府が設定します。日本銀行は物価安定目標を達成する。それを決めるのは政府です。政府は財政政策もやっていますので、財政政策と金融政策の究極的な目的は整合的でないといけないですよね。
でも、例えば2%の物価安定目標を達成するには色々なやり方があります。どのやり方をとるかは完全に日本銀行に任されていて、日本銀行が責任を持って実行すべき話です。だからこそ経済財政諮問会議で日銀総裁がいらっしゃって報告するんです。だから起こったことすべてが、政府が責任を持つという意味ではないと思うんです。そこはちゃんと役割分担があって目的の設定とその目的達成の手段の自由と、それは違うものだということだなと思います
ーーこの先の利上げ判断についてはできるだけ慎重に行うべきとお考えですか?
一般論として言えば、慎重にやるべきだと思います。別に慎重にやったからといってそれほどリスクが増えるわけでもないですし。今利上げ局面ではありますがどれぐらいのスピードで政策金利も同じように上げていくかという点では、若干ビハインドザカーブというか、まず実態経済が先行してそれについていくような形で(利上げを)やる方が安定するんじゃないかなと思います。
ーー今後タイミングを判断するにあたり、どういう経済状況や指標を判断材料とするべきとお考えでしょうか?
やっぱり実質賃金が大事ですね。実質賃金が上がってくるとかなり自信を持って政策金利を上げていこうかという方向になると思います。
今はボーナス月は実質賃金がプラスになりますが、ボーナス月がはずれるとマイナスになってしまうので微妙なところに来ています。来年の3月の春闘がどうなるか。アメリカの関税政策が日本の産業にどういう影響を与えているかということを良く見て判断されたらいいと思います。
円安は「大きな悪影響はない」 見るべきは「水準」「スピード」
ーー円安が進んでいますが日本経済にとってはプラスマイナスどちらが大きいとお考えですか?
(※取材した10月24日の円相場は1ドル=152円台前半~153円程度で推移)
(円安の)水準を考えるのと、スピードを考えるのとは違います。
スピードを考えるときは乱高下するのは企業にとって大変な重荷になります。投資計画が立てられないので。
しかし水準が安定していればそんなに大きな悪影響はないはずなんです。典型的には自動車産業は日本の代表的な輸出産業ですが、これは圧倒的に円安の方が収益も上がります。
既にアメリカに相当投資していますから、ドル建ての収益を円に換算すると相当の利益の増大になり利益が上がる。そうすると賃金も上げられると。
一時期デフレの真っ最中も含めて、投資がなかなか盛り上がってこないときに、輸出産業は結構投資してくれました。今後も世界中の最先端の自動車企業が競争していますからそこは積極的に投資をしていくということで、円安というのは世界のマーケットと日本の投資を結びつける非常に良いきっかけになり、それが賃金の上昇に結びつくということです。
それから先ほど繰り返しですけど、積極的に投資をしている企業は輸出企業が多いということで、輸出企業のけん引力というものは大事だと思いますね。
ーー最近は150円前後くらいでの推移ですがこれくらいの水準であれば、プラスの面が大きいということですか?
私はそう思います。今のようなレベルで安定していればメリットは大きいと思います。
ただし未来永劫そうなるというわけではなく、基本的に為替レートは金利差で決まります。
もしこれまでに比べて国内経済も回復してもし金利が上がってくる気配があれば、金利差が縮まって円高の方向に行くので、一般的にはこれからどんどん円安が進むとは思えないですけどね。
・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】
・【全文公開】トランプ大統領「日本という国を尊敬」日米首脳会談で「日本もかなり自衛隊や防衛を増加すると聞いている」など冒頭発言
・「息子のあんたが責任を持って殺しなさい」8年間の孤独な介護の末、91歳の母親の命を絶った男性の苦しみ “介護殺人”を防ぐには【news23】

