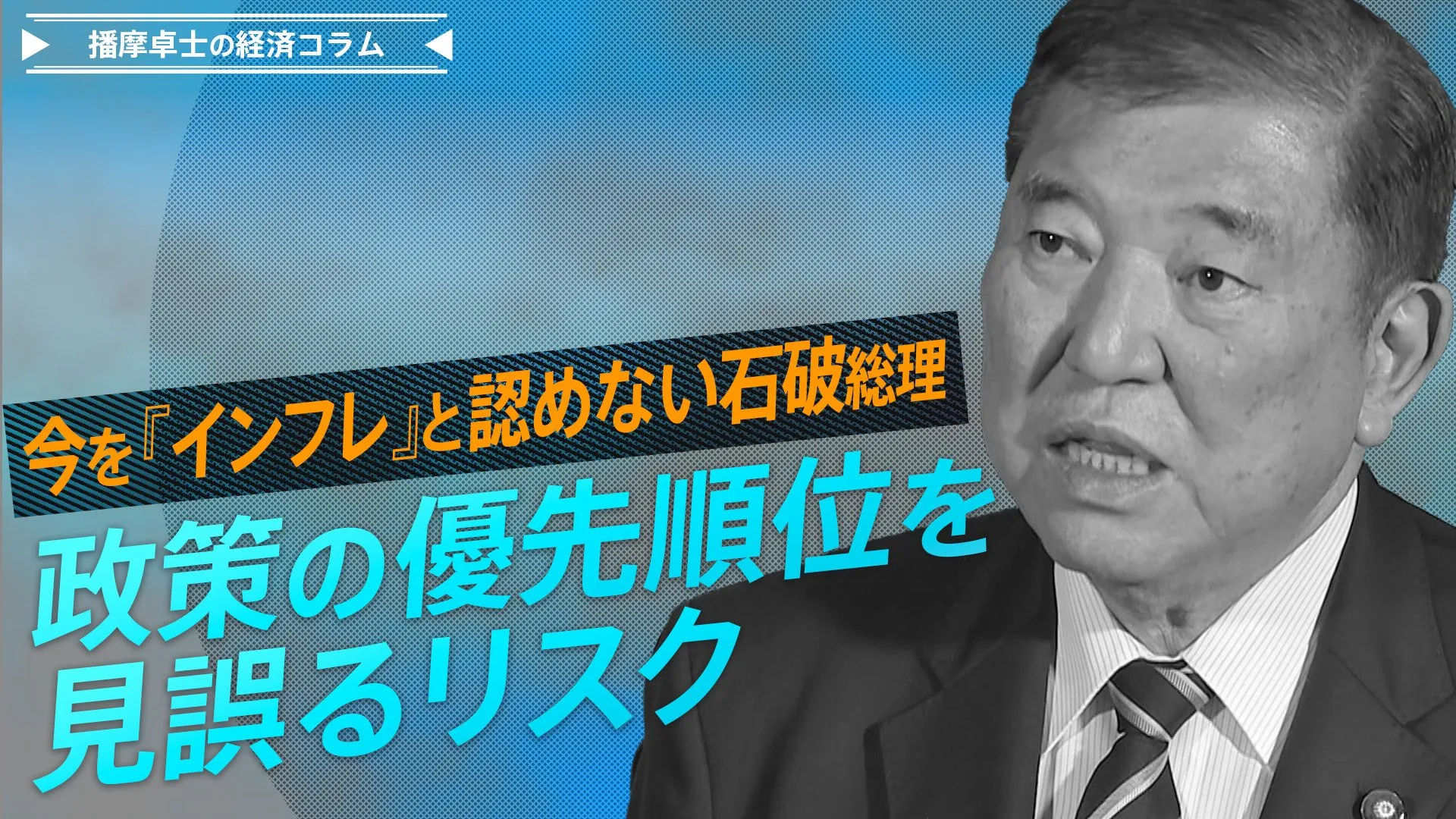
これだけ物価高が続いているのに、総理が頑として「インフレ状態」にあることを認めないという奇妙な光景が、国会で繰り広げられました。政治的な制約が色々あるにしても、現状を正しく認識しばければ、正しい政策など打てないと強く感じる一幕でした。
【写真を見る】今を『インフレ』と認めない石破総理、政策の優先順位を見誤るリスク【播摩卓士の経済コラム】
総理と日銀総裁での認識の食い違い
4日の衆議院予算委員会で立憲民主党の米山隆一氏は、「今の日本経済はデフレなのかインフレなのか」と質しました。これに対して、日本銀行植田総裁は、「昨年も答えた通り、現在はデフレではなく、インフレの状態にある」と答えました。
一方、石破総理大臣は「日本経済はデフレの状況にはないが、デフレから脱却はできていない。今インフレと決めつけることはしない」と答えたのです。米山氏は「デフレ、インフレ、どちらでもないの3つの内、どれか?」と畳みかけましたが、石破総理は「再びデフレに戻らないかどうか、はっきりしないからだ」と返答し、頑として、インフレであることを認めませんでした。
国民が3年以上も物価高に苦しみ、実質消費が2年連続マイナスに陥っているのに、インフレであることさえ認めないというのは、なんと、浮世離れした受け答えでしょうか。
日銀は2%を基準に判断
日銀の論理は、ある種、シンプルです。目標は「2%の物価上昇」なので、変動の大きい生鮮食品を除いても、3.0%も消費者物価が上昇している現状(24年12月)は、「インフレの状態」と言って問題はありません。また、インフレ状態だからこそ、現在進めている利上げも正当化できると考えています。
ただ、「2%の物価目標」が達成されたのかと言うと、「2%が持続的、安定的なものか」を、もう少し見極めたいというのが、今の立場です。
「インフレ」は「デフレ脱却」に直結
その一方で、政府にとっては、それほど単純ではありません。現状をインフレと認めれば、事実上、「デフレ脱却」を認めたことになります。「デフレ脱却」という言葉は、様々な政治的な意味を持っており、「デフレ脱却」となれば多方面に影響が及びます。石破総理は、これまでの政府見解を、忠実に表現しているのです。
政府は「デフレ脱却」の定義として、単にデフレの状態ではなくなるだけでなく「デフレに後戻りしない」ことを挙げています。
将来、デフレになるか、インフレになるかなど、誰にもわかるはずはないのですが、90年代末からのデフレが、余りにも長く、深かっただけに、「後戻り」しないという確証が、政治的には必要です。万一、デフレ脱却宣言後に後戻りなどしたら、政権は吹っ飛んでしまうでしょう。これが第1の理由です。
「デフレ脱却」に至らない方が好都合
第2理由は、現在の様々な政策スキームが、「デフレ脱却」を目標に組み立てられていることです。毎年、繰り返される経済対策、つまり財政の大盤振る舞いも、「デフレ脱却」のためです。
経済対策の結果、延々と続いている補助金は、デフレ脱却となれば、存続理由を失ってしまうかもしれません。利上げが始まったと言っても、まだまだ低い金利も、「デフレ脱却」目標の賜物です。「デフレから完全には脱却していない」という状態は、むしろ政治にとっては、都合が良いと言えるでしょう。
そもそも「デフレ脱却」と言う際の、「デフレ」という単語には、単に、物価の動きだけでなく、賃金が上がること、売り上げが伸びること、失業が減ること、経済が成長することなど、様々な意味が込められています。
デフレ時代が長かっただけに、「デフレ脱却」は、「経済がうまく回っている」ことのように使われているのが実情です。そのことも、「デフレ脱却宣言」を難しいものにしています。
「アベノミクス」への決別も
さらに言えば、「デフレ脱却」が達成されたのであれば、いわゆる「アベノミクス」に完全に別れを告げることが可能になります。
政治資金問題で解散に追い込まれたとはいえ、自民党の最大勢力であった旧安倍派には、いわゆるリフレ派議員も多く、岸田政権も、石破政権も、少なくとも「安倍レガシー」を傷つけるようなリスクは犯していません。
それを解禁することにつながる「デフレ脱却宣言」は、自民党内の力学に変化をもたらしかねません。そうしたリスクには慎重に対処するのが、政治家の知恵なのかもしれません。
正しい認識なしに正しい政策なし
このように色々、事情はあるにせよ、それでも、今の状態をインフレと認めないのは、無理があります。
現在の経済運営上の最大の課題は、インフレ率が高過ぎることです。24年通年の実質賃金は、マイナス幅こそ小さくなったものの、前年比0.2%の減少でした。これで実質賃金は3年連続のマイナスです。賃金が物価に追いつかない状態が3年も続いて、「好循環」を信じろと言われても無理な話です。
連合の芳野会長は、先日のインタビューの際、「去年5.1%もの大幅賃上げを実現したのに、実質賃金がプラスに転じなかったのは、本当に驚きだった」と語っていました。
「胸突き八丁」の、この時期に、ガソリンや電気への補助金縮小・打ち切りやコメ暴騰を放置してきた政策は、愚の骨頂です。政治の最大の仕事は、政策の優先順位をつけることです。それは。正しい現状認識がなしには、まずできません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】
・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】

