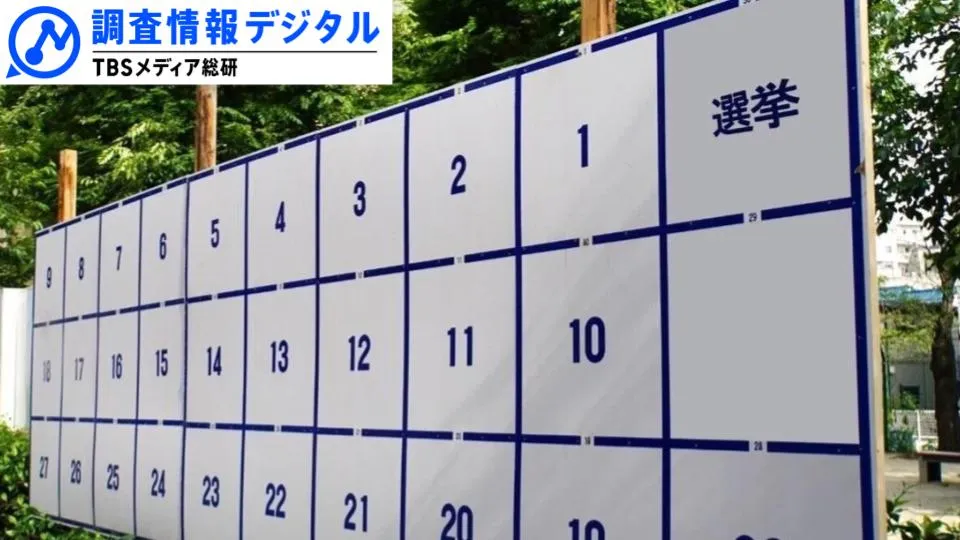
昨年は、東京都知事選、衆議院総選挙、兵庫知事選と、選挙期間中のSNSの効力に注目が集まる選挙が続いたが、それとは対照的に、テレビ局の選挙報道には“物足りなさ”を指摘する声が相次いだ。曲がり角にあるテレビの選挙報道。これを時代に合わせてアップデートするには何が必要かを考えるシリーズの1回目は、選挙の実情などに詳しい東北大学大学院情報科学研究科の河村和徳准教授による提言をお届けする。
ディスインフォメーションやミスインフォメーションがはびこるネット
インターネット選挙運動解禁が議論されていた2010年代の頃、その解禁は政党や候補者が発信する情報の絶対数が増え、政策論争が活発になるのではないか、という期待が非常に大きかった。しかし、近年の選挙を見る限り、政策論争が進んだとは言い難い。
日本以上にインターネット選挙運動が盛んな国々では、相手陣営に対する誹謗中傷などによって国民の分断が進んでいる印象がある。またディープフェイクに象徴されるように意図的に歪められた情報が流布されたり、誤った情報が共有されたりする状況が生じ混乱が生じている。
「表現の自由」「政治活動の自由」を尊重しつつ、意図的に歪められた情報(ディスインフォメーション)や誤解によって広まった情報(ミスインフォメーション)を選挙空間からどう排除するか。インターネット選挙運動時代に入り、世界の選挙民主主義国は頭を悩ませている。
ファクトチェックを行うと言うことは簡単であるが、それを行うコストにプラットフォーマーは頭を悩ませ、メタは第二次トランプ政権発足とともに、フェイスブックやインスタグラムでのファクトチェックの廃止を発表し、Xで導入されている利用者同士でチェックし合うコミュニティーノートを採用する方針を示している。
韓国のように、選挙期間中、選挙管理委員会が徹底的にサイバーパトロールを行うことを選択した国もある。
日本でも、SNSを利用して真偽不明の情報を流したりする動きは近年目立つようになり、とくに動画配信者が視聴数稼ぎのために選挙を利用する動きが目立つ。2024年4月の衆議院東京15区補選でのつばさの党による選挙妨害事件や7月の東京都知事選挙でのポスタージャック事件、11月の兵庫県知事選挙における「二馬力選挙発言」など、2024年は選挙時におけるSNS利用をどうコントロールしていくのかが問われた年となった。
「SNSはオールドメディアを超えた」という言説は適切か
斎藤元彦兵庫県知事が県議会の不信任決議に対して失職を選択したことに伴い実施された11月の知事選挙の際、SNSが選挙結果を左右したと大いに喧伝された。パワハラ疑惑の中で国内世論が斎藤氏に厳しい中で、最終的には111万3911票を獲得した選挙戦術で目立ったのはSNSを使った支持拡大であった。
そして斎藤氏返り咲きを受け、選挙結果を伝えるテレビ番組の中には「ネットの勝利、新聞やテレビといったオールドメディアの敗北」(フジテレビ「Mr.サンデー」11月17日)と評するものもあった。
筆者はSNSが斎藤氏勝利に貢献した部分を認めつつも、「SNSはオールドメディアを超えた」という評価は、ややSNSを持ち上げすぎと思っている。
たしかにインターネット選挙運動を重視する候補者は増えている。都知事選挙の石丸伸二陣営が見せたような、街頭演説からショート動画に繋げていくような選挙運動の手法は、新型コロナ禍によって「高齢者の高齢者による高齢者中心の組織選挙」が機能しづらくなった中、比較的若い候補者の陣営にとって有効性の高い新しい選挙運動の手法だろう。
しかし、兵庫県知事選挙の現実の得票結果を丁寧に見ると、ある不都合な真実も見えてくる。SNSによって斎藤氏が勝利したとするならば、SNSを利用して情報を集める者が多い都市部では斎藤氏の得票が多く、高齢の投票者が多い但馬地方や播磨地方では少ないとならなければならない。しかし実態はそうなっていない。
「兵庫県知事選挙でSNSが結果を左右した」という言説は、「斎藤陣営がSNSを選挙運動で駆使した」という可視化された事実と、「失職を選択した斎藤氏が返り咲いた」という事象を単に結びつけただけなのかもしれない。
選挙結果は、有権者一人一人の投票の総和である。SNSの情報を投票判断に利用する者は、口コミの情報もマスコミの情報も利用している可能性もあるのである。
2024年におこなわれた選挙のうち、SNS利用で全国的な注目を集めた衆議院東京15区補選、東京都知事選、そして兵庫県知事選をふりかえると、共通点があることに気づく。それは、(1)特定の地域で行われる選挙でありながらマスメディア(とりわけワイドショー)によって全国的な関心が集った選挙であった、(2)一般的な市町村選挙と異なり、選挙期間が1週間より長く、選挙運動期間中に動画を作成し配信できる時間的余裕があった、という点である。
2024年は10月に衆議院総選挙が行われているが、国民民主党の躍進を説明する際に若干SNS活用が指摘されるものの、前述の3選挙ほどではない。国政選挙は全国各地で選挙戦が展開され、争点も多岐にわたるため、アテンション・エコノミー(注1)が機能しづらい。
(注1)興味や関心、注目 (=アテンション) をひくような情報によって、クリックを促し、より多くの広告をみたり、サービスを使ってもらおうとするネット上のしくみのこと
筆者としては、2024年の選挙を見る限り、SNSがオールドメディアを超えたのではなく、オールドメディア(とりわけワイドショー)が注目選挙をつくり、それに動画配信者が便乗していると解釈すべきなのではないか。ないしは、SNSを駆使する候補らから提示されるそれまでの選挙の常識から逸脱した発信にオールドメディアが反応してしまい、SNSの効果が増幅されていると考えるべきと思う。
筆者としては、「SNS対オールドメディア」と二項対立的に捉えるのではなく、視聴数稼ぎの動画配信者とワイドショーを中心としたテレビ報道の間に一種の共生関係が生まれていると思っている。ワイドショー番組における政治の採りあげ方やテレビ局における選挙報道のあり方も、問われているのである。
インターネット選挙運動解禁の本質とは
2024年に可視化された選挙におけるSNS利用をめぐり、現在、国会において公選法の見直し論議が進められている。具体的には、選挙運動用ポスターに対して品位保持規定を設けることなどが議論されており、選挙におけるSNS利用に関する論点整理も行われているところである。選挙をめぐる様々な事案に対し、知事有志からも2025年2月17日に「民主主義と地方自治を守るための緊急アピール」が発せられている。
インターネット運動解禁が議論されていた時代に想定されていたのは、ブログなどを通じ文字情報を発信することであり、動画をスマートフォンで手軽に作成し配信できることも、選挙運動の動画配信で供託金を超える広告料収入を得ることも想定の外にあった。技術革新やそれに伴う事象が新たに起こったのだから、インターネット選挙運動のあり方を見直していこうという動きには賛同できる。
しかしながら、国会での議論を見る限り、ややインターネット選挙運動の解禁の本質を見誤っている印象を受ける。
そもそも日本の選挙法は、表現の自由を尊重し規制をできる限りかけないアメリカと異なり、認められた選挙運動だけができる「包括的禁止・限定的解除方式」が採用されている。「事前運動の禁止」「文書図画の頒布の制限」「戸別訪問の禁止」などがその象徴であり、公職選挙法を「べからず法」と揶揄する声もある。
日本の包括的禁止・限定的解除方式による選挙運動規制は、大正時代の衆議院議員選挙法(普通選挙法、1925年制定)にまで遡ることができる。選挙運動を制限することで腐敗選挙を断とうとしたことが選挙運動を規制する1つの理由ではあったが、男子普選が実現することによって無産政党の議席増を懸念したことも背景にあると言われる。
ポスター制作費などを公費支出する選挙公営は、「お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るため」(総務省)に導入された選挙運動規制に伴う保障措置と言える。
選挙運動を規制するということは、候補者や政党から提供される情報量を選挙管理委員会が統制することと同義である。すなわち、選挙公営を通じて選管は選挙情報を量的規制していたとみなせるのである。
インターネット選挙運動の解禁は、選管が選挙情報を選挙公営を通じて管理する時代から、候補者や政党は出したい情報を出したいだけ出せる時代へ変わった日本の選挙史上、大きな転換点であった。
候補者や政党が情報を出したいだけ出す時代に、インターネット選挙運動以前からの選挙管理体制では管理しきれない。紳士協定など通用しない動画配信者をどうコントロールするか。韓国のようにサイバーパトロールで抑え込むという方法を採るならば、選管と警察の共同による選挙管理のあり方を根本から変える必要がある。
品位規定を設けただけでは十分機能しないことは政見放送で過激なパフォーマンスをする者がいまだ散見されることから明白である。東京都知事選挙でのポスター掲示板ジャックも、注目を集める手段に選挙公営を利用した行為と十分みなせる。公選法改正は、場当たり的に考えるのではなく、インターネット選挙運動解禁の本質の部分や選挙公営のあり方から議論する必要がある。
SNS選挙全盛時代におけるテレビ局の選挙報道のあり方は?
日本のテレビ局は、公共の電波を利用していることから不偏不党が強く求められる。選挙運動期間の報道が抑制的になりやすいのも、特定の候補者・政党に肩入れしていると思われないための配慮が働いているからである。
不偏不党という立場の延長線上で考えた場合、テレビ局などのマスメディアがファクトチェックの主たる担い手になるという考え方はある。マスメディア全般に対して否定的な(ないしは懐疑的な)見方をする者もいるが、マスメディアほど、ディスインフォメーションやミスインフォメーションを訂正できる資源を有している組織はない。
ただ、筆者としては、マスメディアは投票参加を喚起し投票先を判断する情報を提供する方向により注力する必要があると考える。かつてほどではないかもしれないが、マスメディアには「いまこれが社会的に重要な課題である」と国民に認識させる力は有している(だから動画視聴を稼ぎたい者はマスメディアが採りあげそうな話題を提供しようとするのである)。そうした立ち位置を認識し、選挙報道(ワイドショー番組を含め)がどうあるべきか考えるべきである。
また、テレビ局は動画を容易につくることができ配信できるようになった時代になったことをふまえ、そうしたSNSで一般人がつくる動画とどう差別化できるか考えるべきである。一般の視聴者が流せる風景を流すだけのテレビ局は、選挙報道を行う存在として失格である。
それでは、具体的にどのようなことが考えられるのか。それは、インターネット選挙運動の本質の議論から導き出せる。
【提言1】候補者間・政党間比較を意識した報道
インターネット選挙運動時代の候補者や政党は「出したい情報を出したいだけ出す」ということを既に述べた。裏を返せば、彼らは「出したくない情報は出さない」のである。すなわち、都合の良い情報だけが候補者や政党から垂れ流されるのがSNSを中心とするインターネット選挙運動時代と言える。
しかし、それでは有権者が必要な情報は得られない可能性が高い。有権者の中には候補者や政党が掲げる公約を比較したいと考えている者もいる。マスメディアは、有権者が比較できる情報を提供することが求められる。
これは多くのマスメディアが実践している。候補者や政党にアンケートを行い、それを新聞は紙上で、テレビ局はニュース番組などで報道している。ただ、こうしたアンケート手法は使い古された側面もあり、新味に乏しい。
アメリカの大統領選挙のようにテレビ討論会をテレビ局主導で行ったり、国政選挙の際に日本記者クラブが行っている党首討論会のようなことを行うことは可能であろう。討論会を仕切るコーディネーターをどう調達するかといった課題はあるものの、こうした企画は視聴数稼ぎの動画配信者にはできないことである。
NHKや毎日新聞などが行っている、アンケート情報を元に有権者が質問に答えていくと考え方が近い政党や候補者がわかる「ボートマッチ」システムを構築し、それを夕方のローカルニュースの報道と連動させるという手法も考えられる。
ローカルテレビ局でシステムを一からつくり、選挙公約を数値化するコーダー(研究者などの有識者が想定される)を集めることは難しいが、系列局や地元紙などと連携して取り組むことは可能であろう。
【提言2】時間軸を意識した選挙報道
出したい情報を出す候補者や政党、そして刹那的に視聴数を追求する動画配信者たちは目先の利益に注目しすぎて、提供している動画のもつ歴史的な価値はあまり関心がないと思われる。動画を個人で保存する容量が限られているのが一般的であるし、動画を長期にわたってアップしておくインセンティブが見当たらないからである。
しかし、テレビ局には過去の(それもインターネット選挙運動解禁以前の)映像がアーカイブされている。このアーカイブはテレビ局にとっての資源であり、現職候補の公約の検証や選挙風景の変化など、有権者に気づきを与える選挙報道を創り出すことができると思われる。
たとえば、現在、筆者は非言語情報が政策認知や投票行動に与える影響についての研究プロジェクトに参加しているが、投票行動を左右する情報は文字だけとは限らない。候補者の笑顔や声のトーン、候補者が行う辻立ちを囲んでいる面々の表情やその年齢構成、こうした非言語情報も投票先を考える上で有効な情報になる可能性もある。非言語情報の記録もあるテレビ局には、大きなポテンシャルがあるのである。
【提言3】「続きはWEBで」の仕掛け
ただし、テレビ局には番組の時間という制限があるし、民放には視聴率という壁もある。選挙報道は重要であることはわかっていても、そうした制約から逃れることはできない。そこで大事になってくるのが、「続きはWEBで」という仕掛けである。
近年は、「TBS NEWS DIG」など系列各局のニュースをキー局のサイトにまとめて比較する動きが進んでいる。こうしたサイトを構築することは、選挙報道に接しやすくする効果を生むことは間違いない。
ただ、夕方に流れたニュースをただ陳列するだけでは勿体ない。テーマによって特集を組み深掘りする仕掛けは必要である。
たとえば、NHKの「選挙WEB」のように選挙関連ニュースだけではなく、さまざまな情報を凝縮したサイトを構築することによって、テレビ局、とりわけ民放ローカル局が選挙報道を行う社会の公器として重要であることをより認識してもらえるのではないか。NHKの「選挙WEB」は全国の大きな選挙を網羅しているが、おらが村の村長選挙などはフォローしていない。注目されにくい選挙であってもWEBを利用してフォローすることは、ローカル局の生き残り戦略としても有意義のように思える。
またNHKが障がいのある有権者向けに作成している「みんなの選挙」のように、ニュース動画だけではなく、選挙制度の解説や課題の指摘などを指摘するサイトをつくることも有意義ではないか。それは主権者教育を行う上での素材につながるからである。
新聞ではNIE(Newspaper in Education)があるように、選挙報道サイトを主権者教育に活用してもらうつくりにするという発想もあってもよいだろう。
選挙報道の人材育成という課題
そもそも選挙はPDCAサイクル(注2)が機能しづらい分野である。選挙は毎年あるわけではないため、記者の経験値がなかなか上がらない構造があるからである。また選挙制度が研究者すら理解しづらいほど複雑であることがそれに輪をかけている。
(注2)PLAN(計画)、DO(実施)、CHECK(評価)、 ACTION(改善)の4つの視点をプロセスの中に取り込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法のこと
実は、筆者がこれまで行ってきた研究の中には、マスメディア関係者との交流がきっかけのものが多い。
政党相乗り選挙の研究は北陸新幹線金沢延伸との関連性に問題意識を持っていた北陸中日新聞との連携で進められたものであるし、平成の大合併についての研究は北陸朝日放送のドキュメンタリー番組と深くつながっていた。農業従事者意識調査は朝日新聞仙台総局との連携の中進められたものであるし、近年行っている地方議員のなり手不足に関する研究もNHKが実施した地方議員アンケート調査への協力が端緒である。
人口減少によって日本全体がシュリンクしていることに加え、広告料収入が減る中で選挙報道にかかる人材育成をテレビ局だけで行うことは容易ではないかもしれない。
我々研究者も人材育成にどう貢献するか、問われているように思う。
〈執筆者略歴〉
河村 和徳(かわむら・かずのり)
1971年静岡県生まれ。
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程を単位取得退学後、慶應義塾大学法学部専任講師(有期)、金沢大学法学部助教授を経て現職。
2025年4月より拓殖大学政経学部教授。
専門は政治学、日本政治論。東日本大震災以降、被災地における政治・行政の分析や、電子投票など選挙ガバナンスの課題などに力を入れて研究を行っている。
著書に「電子投票と日本の選挙ガバナンス(慶應義塾大学出版会、2021年)」など。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】
・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】

